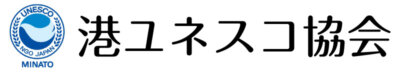盆栽 日本の伝統文化 実演と体験
■日時:
2025年3月8日(土)
13:30ー16:00
■会場:
港区立生涯学習センター101号室
港区新橋3-16-3
(JR新橋駅鳥森口から徒歩3分)
■定員:30名(申込み多数の場合は抽選)
■参加費(材料費・保険料):
*港ユネスコ協会会員…3,000円
*一般の方………………3,500円
■受付期間:
*2025年2月4日(火)ー2月21日(金)
*お申込みはホームページから
■内容:
*盆栽の歴史・文化の説明
*講師によるデモンストレーション
*各自盆栽作り実習(小品盆栽・桜)
*道具無料貸し出し
*完成作品はお持ち帰り頂きます。
(お持ち帰り用の袋をこ持参下さい)
講師
有限会社 清香園
倉成 裕也
◆講師プロフィル
農業高校卒業後、さいたま市で開催された世界盆栽大会で初めて盆栽に触れ、盆栽の道へと進む。盆栽のレンタルや管理・消毒など多岐にわたって活動中。日本の古くからの文化である盆栽の普及に尽力。
■清香園/企業説明
江戸末期、浮世絵にも梅や松の盆栽が多く登場し、庶民の文化としての園芸が花開いた時代、初代庄之助が現在の台東区根岸のあたりに創業いたしました。
当時、根岸の里は上野の山から湧き出る清水が豊富で、後の明治・大正期にかけても画家や書家などの文人墨客・歌舞伎役者・長唄の師匠・商家の別荘などもある、独特の雰囲気のある場所であったと伝え聞いております。
三代目釜次郎
清香園の屋号の由来は、その当時根岸周辺に梅林が多かったこと、また梅の盆栽を多く手がけていたことから「清く香る園」といたしました。二代目初五郎は、薄鉢で竹の盆栽を作ることを得意とし、三代目釜次郎は石付き盆栽を得意としました。この釜次郎の代で太平洋戦争の戦災を逃れて大宮の盆栽村に移住。現在は、四代目の登美男が園主で、盆栽種全般を扱っております。多くの樹種を手がけ、種別に研鑽して参りましたことは、清香園の貴重な財産であると考えております。
さいたま市北区の盆栽町(通称盆栽村)には毎日、海外からのお客様が訪れています。
世界に誇る日本の園芸文化、盆栽を微力ながらも、守り伝えて参りたいと考えております。
ホームページURL:盆栽 清香園 ~盆栽の作り方・育て方は彩花盆栽教室へ(https://www.seikouen.cc)